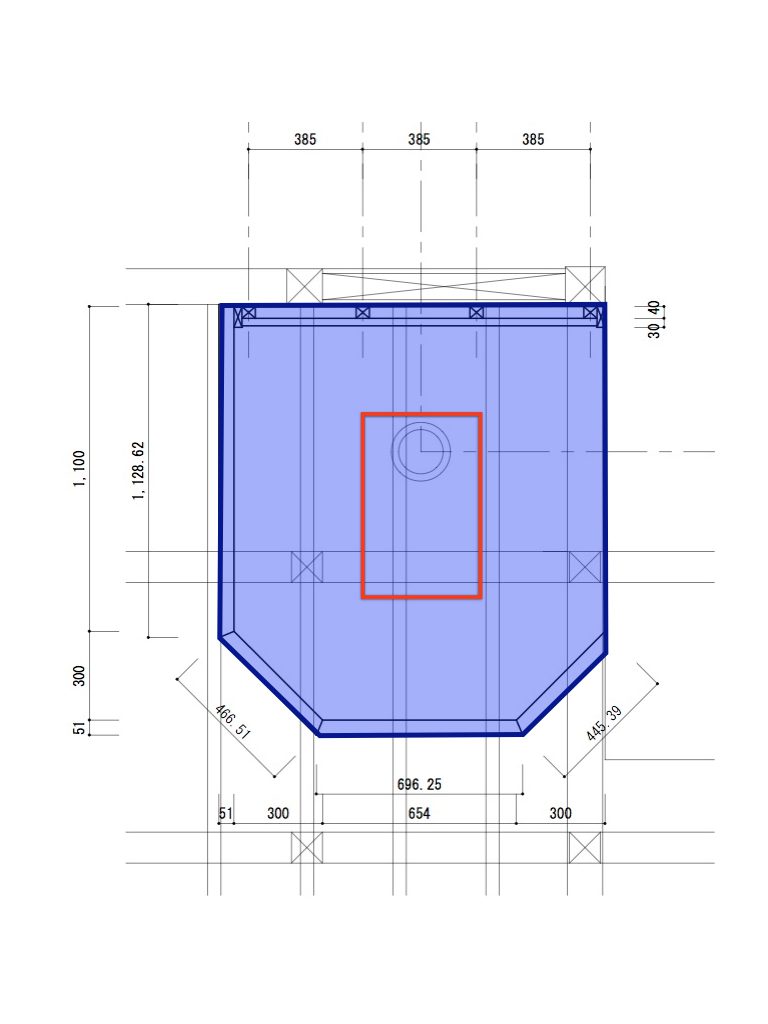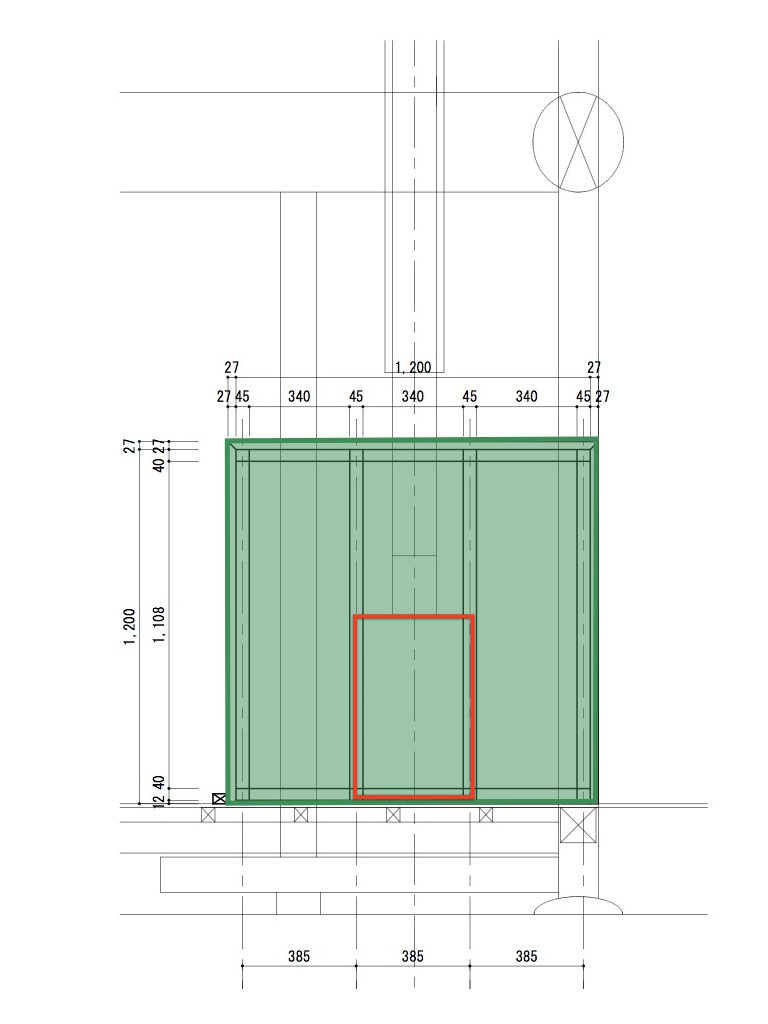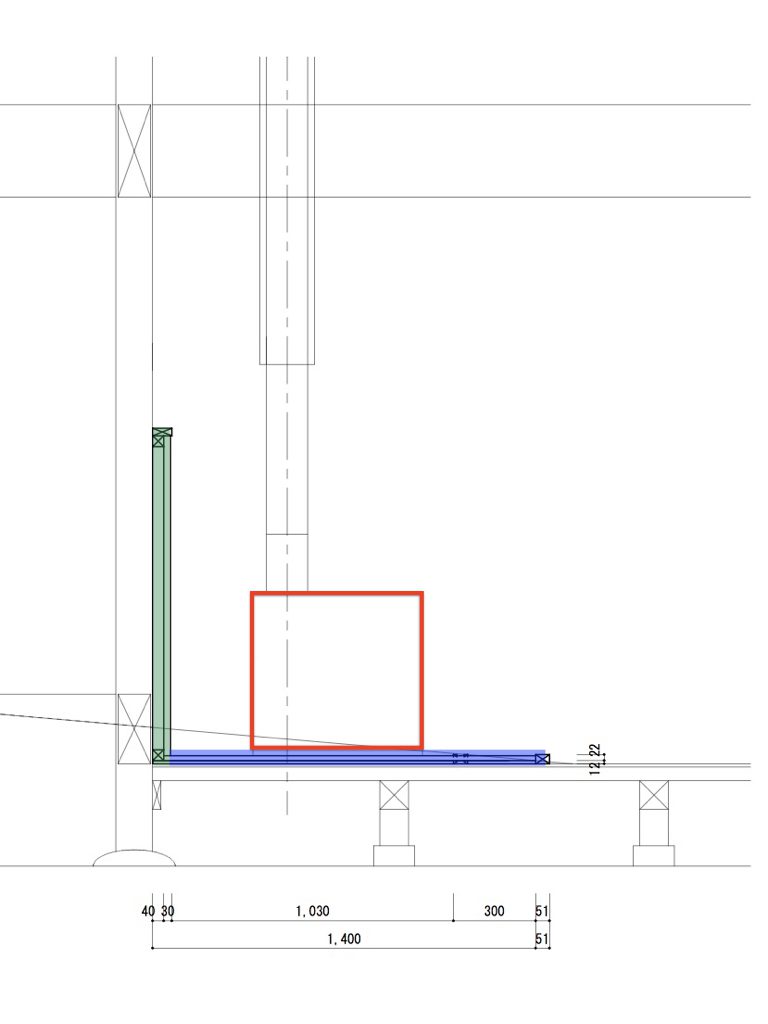朝活(朝の1時間を使用)で庭木の剪定を行なっています。
先日から始めたアラカシの剪定が終わりました。
<ビフォー>
<アフター>
このアラカシは大きく(樹高7m程度)、樹勢も強いです。
一方、二階建ての建物(上写真の右側)が近接しています。
これ以上大きくならないように、下写真の点線内に収まる樹形となるように毎年剪定を行なっています。
また、二階建ての建物があり風が通らないため、毎年、樹高の下半分で「うどん粉病」が発生しています。
被害を拡大させないよう、剪定で罹病した葉を落とすようにしています。
下写真で、葉の表面にうどん粉のような白いものが付着しているのがうどん粉病です。
さて、アラカシが終わりましたので、続いてはこちらのカイヅカイブキです。
カイヅカイブキはヒノキ科(ビャクシン属)の樹木です。
ヒノキ科だけあってヒノキに似た葉をしていますが、木を痛めるような強い剪定をすると、先祖返りしてスギのような葉になってしまうという面白い?特徴があります。
大気汚染には強いのか、国道などの中央分離帯に植えられているのをよく見かけます。
しかし、樹形が乱れ、徒長枝が盛んに出ているものが多く、さすがに劣悪な環境なのでしょうね。
さて、このカイヅカイブキも大きいです。
隣に立ててある高さ10尺(3m)の三脚と比べると、樹高は5m以上ありそうです。
ところで、この三脚では一番高いところまで届きません。
木の頂上部をどのように剪定するか?
木に登るわけですが、この木の頂上部で両手を離し刈り込み鋏を使えるものか?
実はこの木の頂上部には天然の足場ができており、両手を離して作業できるようなっているのです。
では、木の頂上まで登ります。
頂上まで登ると主屋の屋根が低く感じます。
高所恐怖症気味ですので、足がすくみます・・・
足元は数本の太い枝が天然の足場を形成しています。
また、玉造りが腰回りをサポートするように囲んでいます。
ちょうど建物に影が映っていますが、このような感じで立っています。
一見危なそうに見えますが、三脚の上部で立っている以上に足元は安定しています。
この木だけでなく他の高木も同様に、頂上部には太い枝で天然の足場が形成されています。
自然とこうなったのか?、それともこのように枝を配したのか??不思議です。
三脚側から側面を刈り込んでいるとき、その頂上部に野良猫が登ってきました。
猫は木登りが得意なだけあって、余裕の表情ですね。
このように剪定を行い、5日(5時間)ほどかかって終了しました。
下写真は、左から剪定済みのマキ、アラカシ、カイヅカイブキです。
大きい木は、残すところ2本(モッコク、チャボヒバ)となりました。