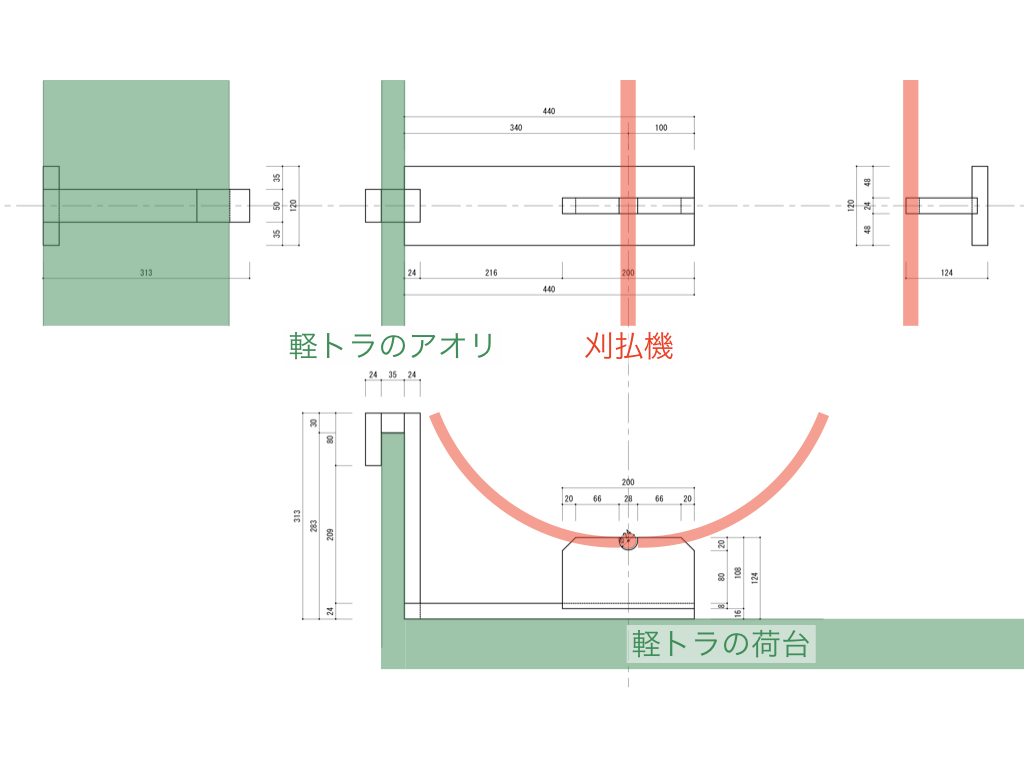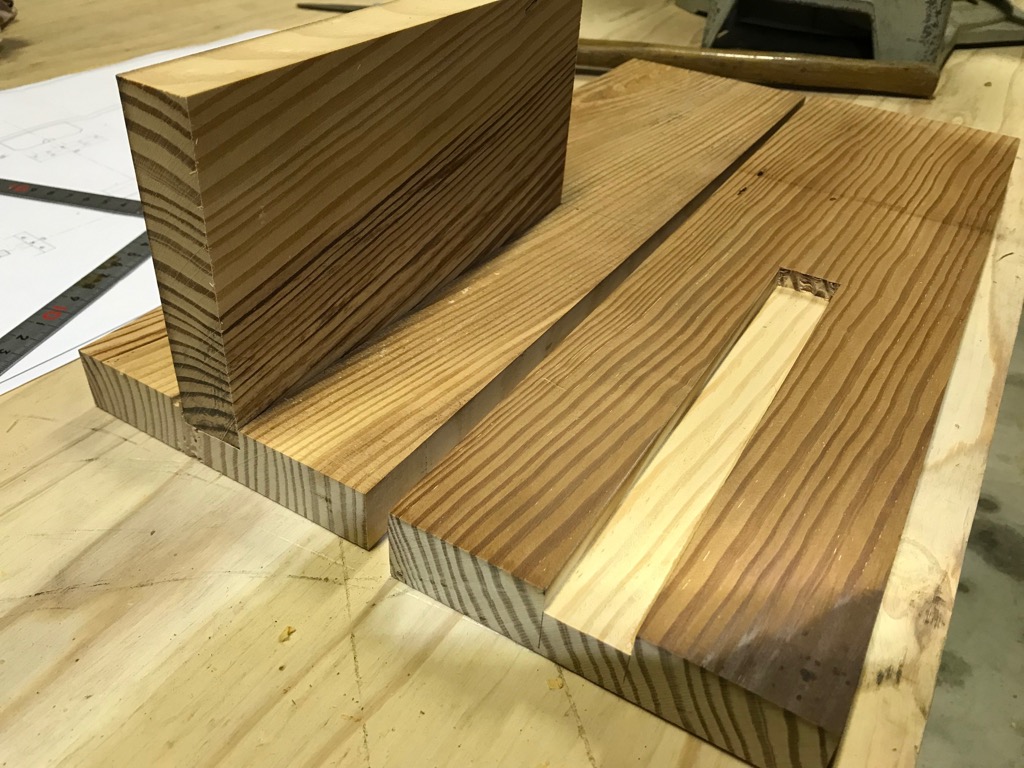先般、公道沿いにプランター(シバザクラを植栽)を設置しました。

プランターの周囲は上写真のとおり雑草が蔓延っています・・・。
主な雑草はスギナ、二ガナ、ヨモギ、そして笹です。
草取りするにしても、強力な根を張っている笹だけは容易には草取りができずに厄介です。
かと言って、除草剤を使って根ごと枯らしてしまうと土が流れてしまいます(公道との間に50cm程度の段差があります)。
そこで、時間をかけて笹から芝(管理が容易で見た目も良い)に移行させたいと考えています。
と言うことで、下写真で朱色破線の範囲(1坪程度)について笹を掘り起こして根ごと除去。

上写真で右側(公道側)は斜面になっているため笹は除去せず(土の流出防止)、今後の芝の広がりとともに笹から芝に移行させる考えです(定期的に刈り込めば笹より芝が優勢になります)。
一方、上写真で左側は車庫前で砂利敷きになっています。
砂利敷と言っても畑だったところに、そのまま砂利を敷き均しただけの安普請のため直ぐに砂利が沈んで年中草取りしている有り様です。
沈んだ分の砂利を補足するのにも手間と費用(5年に1回、3〜4万円)を要しますし、そもそも外部から持ち込みたくないと言う思いもあります(特にRC材)。
そこで、車庫前も芝生にできないものかと思っています。
砂利敷きから芝生へ変更するにしても、土木仕事により一気に行うのではなく、自然の力を生かして少しずつ行うため(10年計画?)、今回の芝張りをその取っ掛かりにしたいと言う考えもあります。
さて、芝張りは、いつもとおり播き芝の手法で行います。
既存の芝生から伸びたランナーを切って集め、それを使えば良いのですが、今春にアプローチの芝生も拡張する予定のためホームセンターで1束(1m2分。約500円)だけ買ってきました。

約1坪の面積に芝を張るには通常、上写真のものが3束必要になりますが、播き芝であれば1束9枚のうちの1枚(つまり1÷3÷9=1/27の量)あれば十分です。
適当な大きさに切って植え付けます。

本来はランナーをバラして全面に播くようにしますが、このほうが楽チンです。
目土を被せて転圧、水をたっぷり与えて完了です。

ところで、下写真が今回掘り起こして除去した笹の根です。

わずかな面積(1坪程度)にも関わらず凄い量で、さすが笹の駆除が大変だとされるはずです。
我が家の敷地は長年にわたり除草剤を多用してきたこともあって地下茎を伸ばして成長する笹(あと球根植物)が蔓延っています。
このため、笹の駆除をテーマにしたブログ記事をいくつかアップしていますが、そのうちの「除草剤に頼らない笹の駆除方法」へのアクセス数(日毎)が下図です。

1日100から200のアクセス(主にGoogle等の検索サイトから)があり、ブログ全体の1〜2割をこの記事が占めるような状況です。
このことから、敷地内の笹に悩んでいる方は我が家に限らず多くみえるのだと思いますし、敷地内の笹が問題化する背景には除草剤の影響があるように思えてなりません。
今回ブログ記事にした笹から芝への移行についても、うまくいくかどうかはわかりませんが、除草剤を使用しない笹の駆除方法の参考になればと思っています。