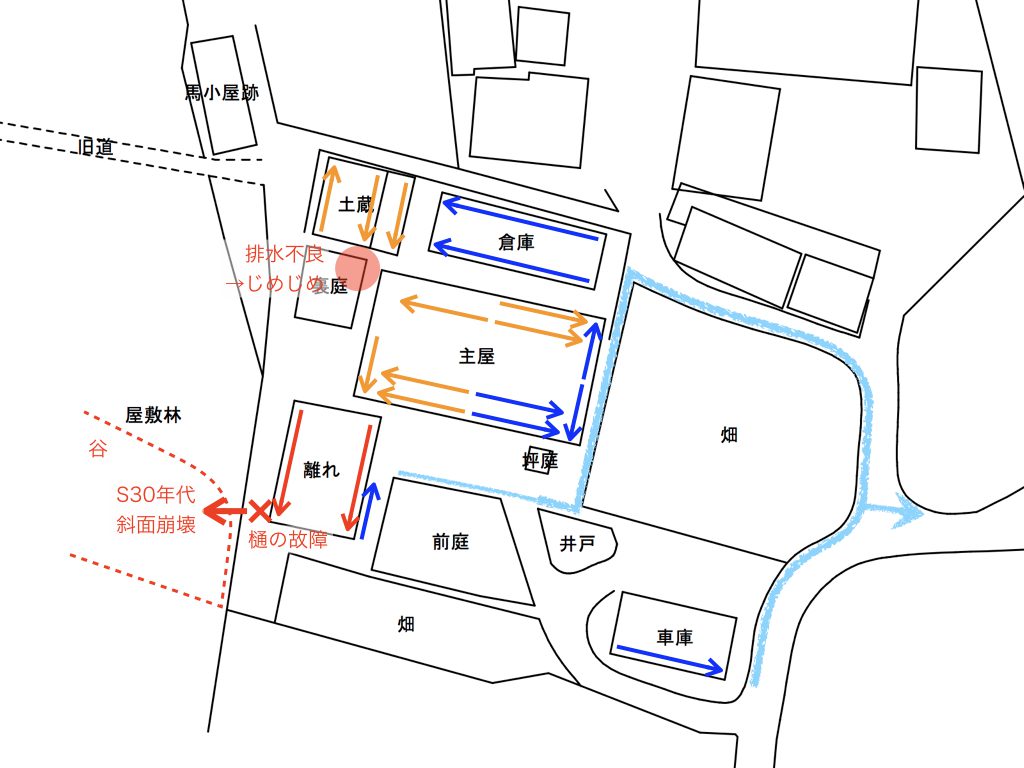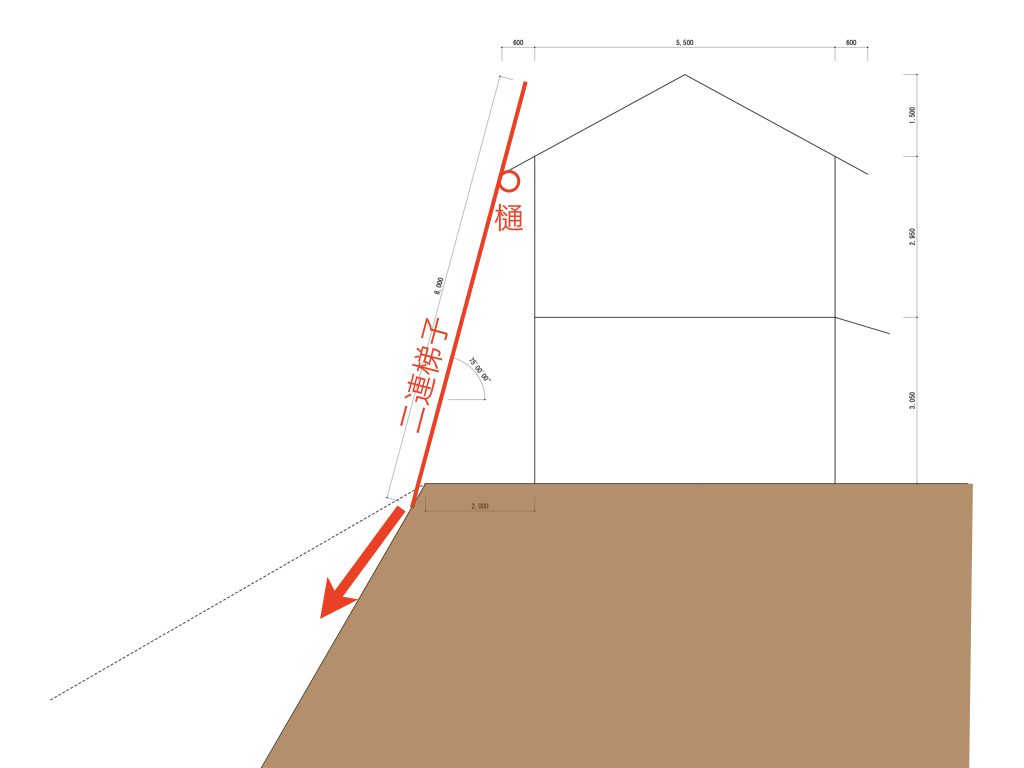昨年の11月下旬まで朝活(早起きして1時間作業)として庭木の剪定をおこなっていました(下写真は完了後の様子)。
冬の間は樹木も成長しませんので、4ヶ月経った今も剪定直後の状態が維持されています(下写真)。
変わったところと言えば、11月下旬にはまだ緑が残っていた芝(日本芝:高麗芝)が休眠期で茶色く枯れた状態になっています。
ちなみに、芝が張ってあるところは元々は砂利敷きだったのですが、そのときは里山から吹き飛ばされてくる落ち葉(主に竹)の掃き掃除で大変な思いをしていました。
里山の整備により落ち葉自体が大幅に減ったこともありますが、芝生にしたことで落ち葉があっても目立たなくなり、結果、ほとんど掃除しなくても済むようになりました(上写真は掃除していない状態)。
また、掃除をするにしても芝生の場合は熊手を使ってサッと掻き集めることができて楽チンです(砂利敷きの場合は熊手が使えないため意外と面倒です)。
ただ、手間の面では芝生は夏場の芝刈りが必要となりますので、芝生にしたことで決して省力化されたわけではありませんが、ズボラな自分にとっては適当に芝刈りしている方が性に合っているように感じています。
閑話休題。
あまり変化のない冬の庭木ですが、それでもサザンカに始まり、センリョウ・マンリョウ・ナンテン、そして春に近づき、ロウバイ、ウメ、サンシュユ、ツバキ、ハクモクレンと花を咲かせて楽しませてくれています(下写真はサンシュユ、3月18日撮影)。
サザンカは冬の間、長く咲き続けましたが、ツバキにバトンを渡すように花の時期が終わりましたので剪定することにします。
ビフォー&アフターでほとんど変わっていないように刈り込み鋏を使って軽く整えた程度です。
この程度の剪定で意外にも来冬までこの状態から余り変わらず、花もたくさんつけます。
以前は枝の透かしなど、若干強い剪定をおこなっていましたが、徒長枝が出て夏場にはボウボウになっていました。
サザンカに限りませんが、なるべく樹木に負担を掛けない剪定(弱剪定)をおこなうようにすれば、結果的に剪定作業も楽になるように感じています。
そして現在、満開時期を迎えているのがハクモクレンです。
たくさん花がついていますが、以前は下写真のように少し寂しい状態でした。
そして朱色の円で囲んである箇所が握りこぶしのように肥大化しています。
このように肥大化したのは毎年同じ箇所で切り詰め剪定をおこなったためですが、肥大化したところで枝はたくさん出ているものの花数は少ないことから、良い状態ではないのかもしれません。
かと言って、この肥大箇所を切り落とすのは強剪定になり樹木に負担をかけますので、1年に1箇所づつ落とし違う枝を伸ばすようにしています。