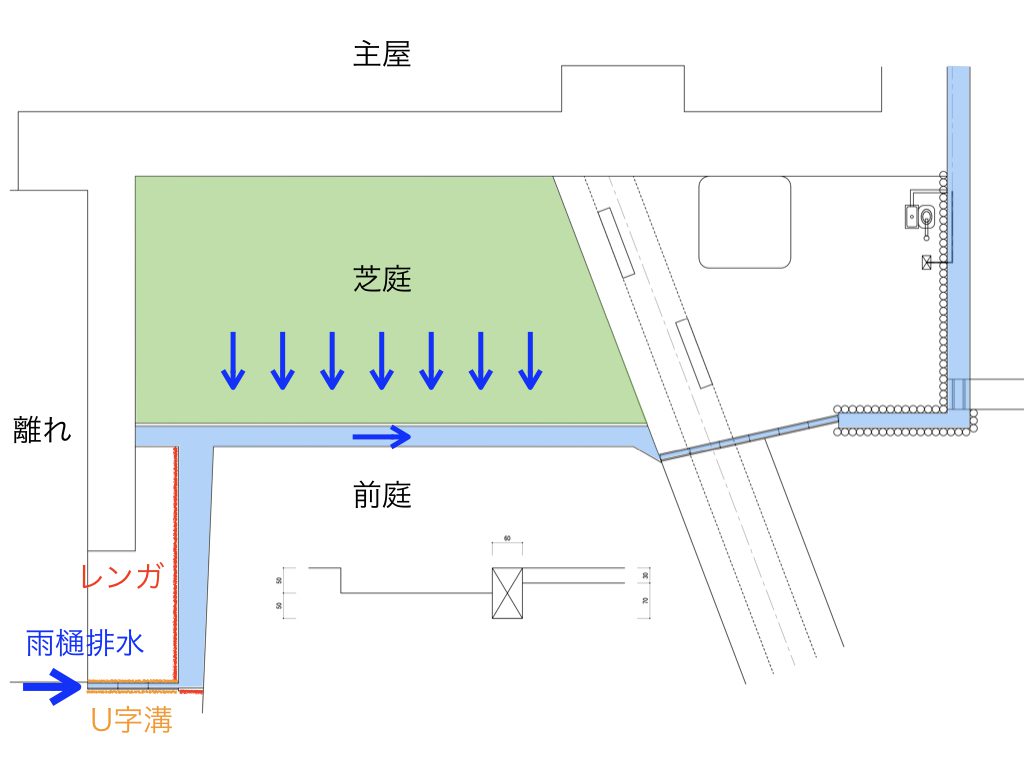4月上旬には秋に剪定した姿のままだった庭ですが、若葉が芽吹き、すっかり景色が変わりました。
上写真にも写っていますが、先の連休頃にはツツジが満開になりました。
たくさんの花をつけ、まさに満開です(^_^)
ところで、ツツジは花が散って間もなく翌春の花芽ができるそうです。
つまり、花芽ができるまでに急いで剪定しないと翌春の花付きが悪くなってしまうと言うことです。
もちろん剪定しなければ翌春もたくさんの花をつけますが、木は大きくなる一方です・・・。
満開だったツツジは現在、下写真の状態になっています。
まだ花の蜜を吸いに来る昆虫もいるかもしれませんが、来春も花を楽しめるように剪定することにします(^_^;
刈り込み鋏を使って表面を軽く刈り込みます。
右側が完了。
左側も完了。
表面を軽く刈り込むだけですので時間はかかりません(小さい木だと5分程度、大きいものでも2、30分)。
それでも我が家には15本以上のツツジがありますので一仕事です・・・(さらにサツキも同程度あります)。
他のツツジも同様に刈り込み、残すは土蔵前のツツジです。
このツツジはほとんど花をつけなかったのですが、一昨年から急に花をつけるようになりました。
以前は上写真でツツジの後ろ側に土塀があったのですが、それを撤去したことで風通しが良くなり花をつけるようになったみたいです(土蔵の壁も塗り替えていますので、光の反射により一帯が明るくなったのもあるかも!?)。
ちょっとしたことですが、植物は影響を受けるものですね。
そんなツツジですが、残念なことに背が高くなり下枝が枯れ上がってしまっています。
ただ、最下部から新しく株立ちしてきていますので、この部分を使って上写真で点線のとおり仕立て直すと良さそうです。
そこで、思い切って数本の主幹(背の高い部分)を根元付近で切り取ります。
せっかく花をつけるようになったツツジが・・・。
最後に刈り込み鋏で形を整えて完了(左にあるのはツバキ)。
現在は土蔵と倉庫との間のスペースに無造作に植えてあるだけですが、お隣の方から「古瓦を使って花壇のようにすると良いかも」とアドバイスをいただきました。
なるほど!いつかやってみることにしましょう!