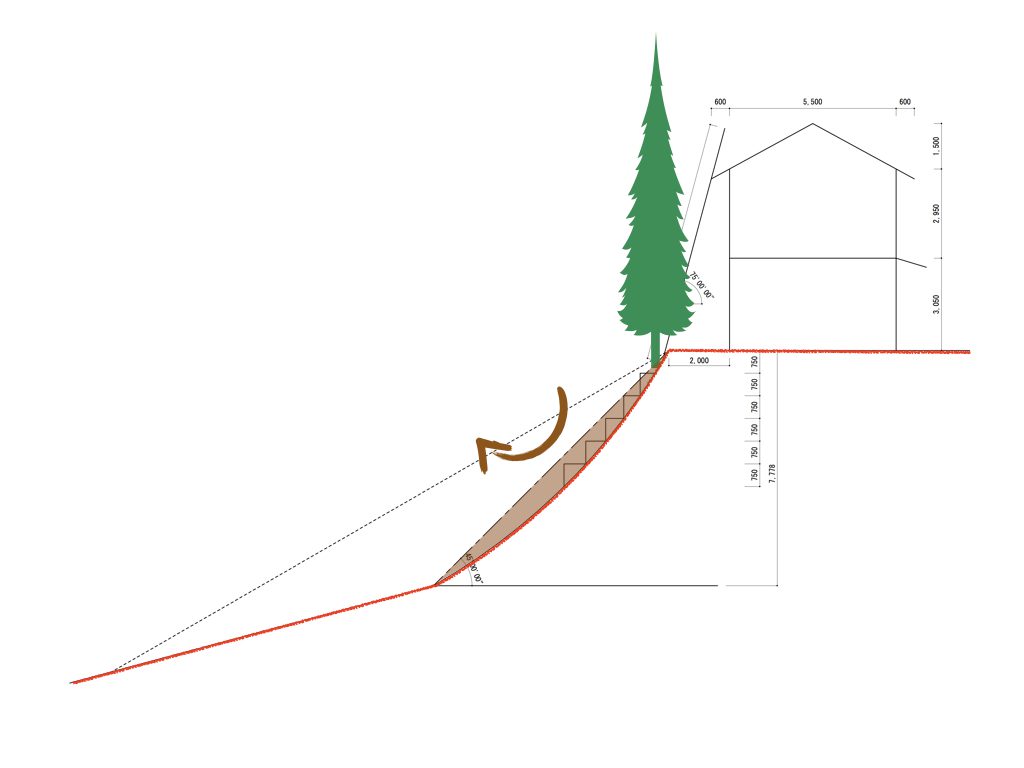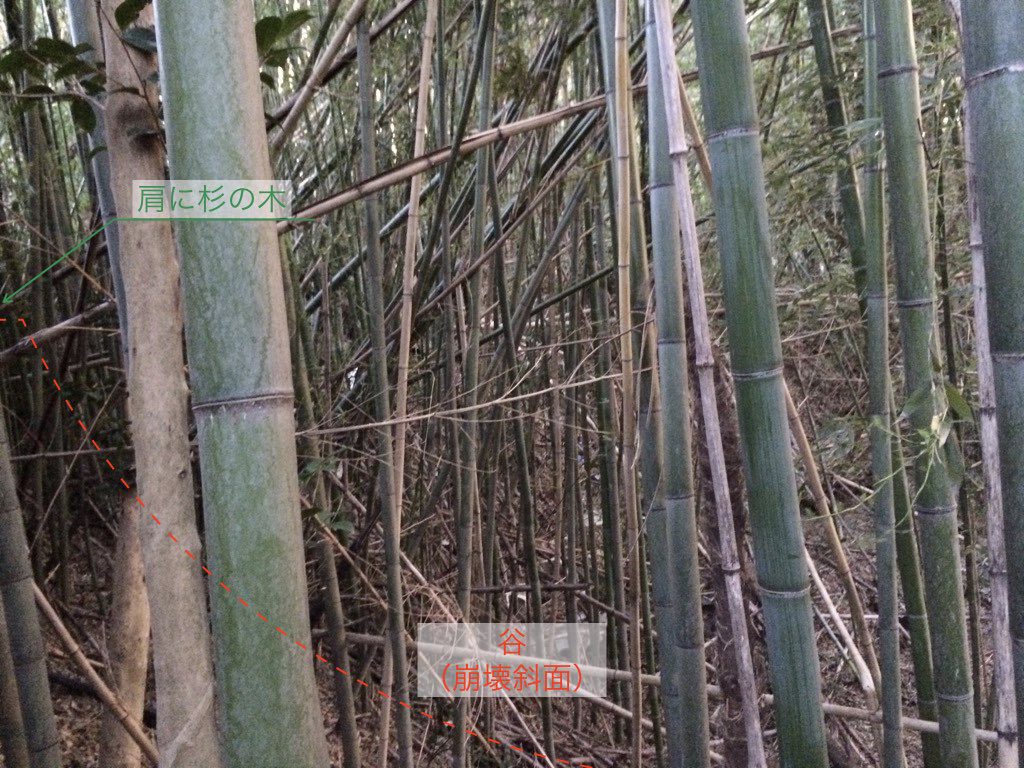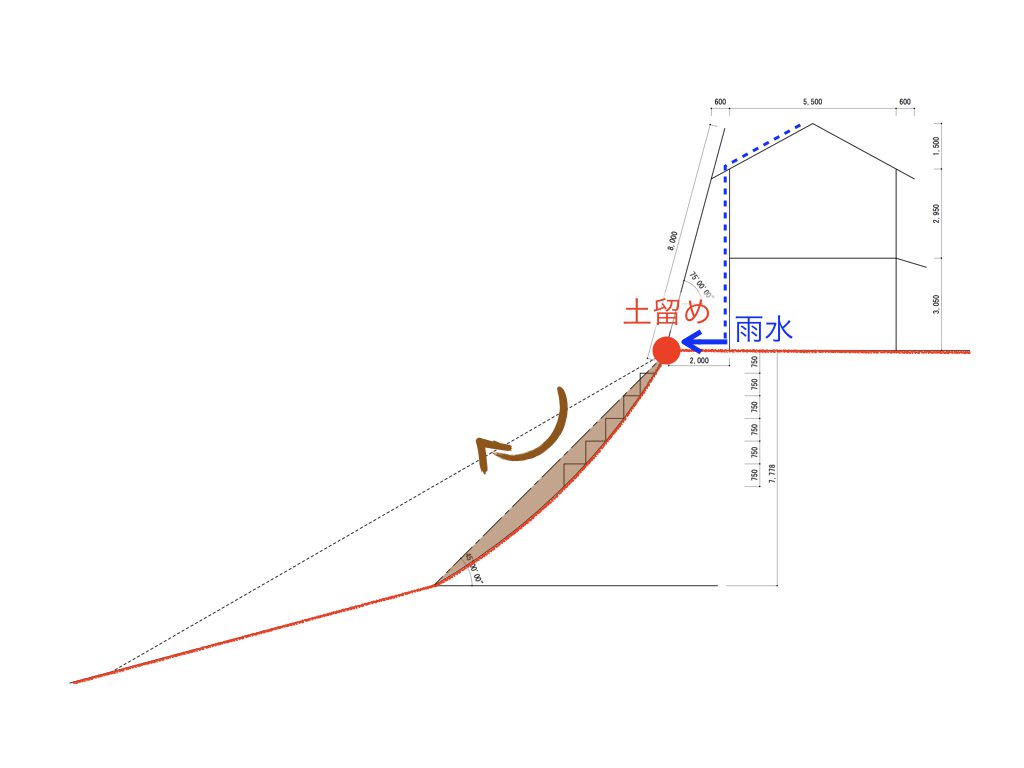一昨年の春、砂利敷きだった主屋(古民家)前を芝庭に変えました。
芝庭と言えば管理が大変と言うイメージがありますが、これまでのところは夏季の芝刈りと目に付いた雑草を折々に取るぐらいしかしていません(特に問題なく生育しています)。
しかし、芝生管理のテキストを読むと、ほかにも施肥や目土入れ、エアレーションなどを行う必要があるとのこと。
この内の目土入れは、床土と同じ用土を定期的(年1回程度)に補足するもので、芝生を若返りさせるために重要な作業とされています。
用土が必要となりますが、門松を作る際に使用した山砂を残してありますので、それを使って目土入れを行うことにします。
目土を入れる前に、除草と掃き掃除(落ち葉やサッチ)を済ませておきます。
目土は下写真の鉢に入っているものを含めて約30リットル分を用意。
芝生の面積(約50m2)から敷き厚は0.6mm(=30L/50m2)となります。
標準的な敷き厚3mmに比べると相当少ない(1/5)ですが、今シーズンはこれで様子を見ることにします。
ちなみに3mmにしょうとすると150リットルの山砂(ホームセンターの小袋入りのものだと約7袋)が必要となり、結構なボリュームになります。
目土を入れるついでに草木灰(薪ストーブで発生したもの)を混ぜて肥料分(石灰、カリ)も補うことにします。
花咲爺さんになった気持ちで灰入りの目土を均等な敷き厚になるように散布。
とは言え0.6mmの敷き厚しかありませんので、外観上の変化はほとんどありません。
この作業を行なっているときに地元の新聞屋さんが集金にみえたのですが、その方は以前ゴルフ場などで芝生の管理(キーパー)をされてみえたとのこと。
そこで色々と教えていただいたのですが、芝生で最も大切なのは除草をメインとする管理作業で、次いで排水性が良いことだそうです。
今回の目土入れでは山砂を使いましたが、年々積層していくことを考えると、より排水性が優れる川砂を使ったほうが良いことも教えていただきました。
ほかにも地元の建材屋さんで扱っている砂利のことなども教えていただいたのですが、こうして話しを聞くとやりたいことが増える一方です(^^;