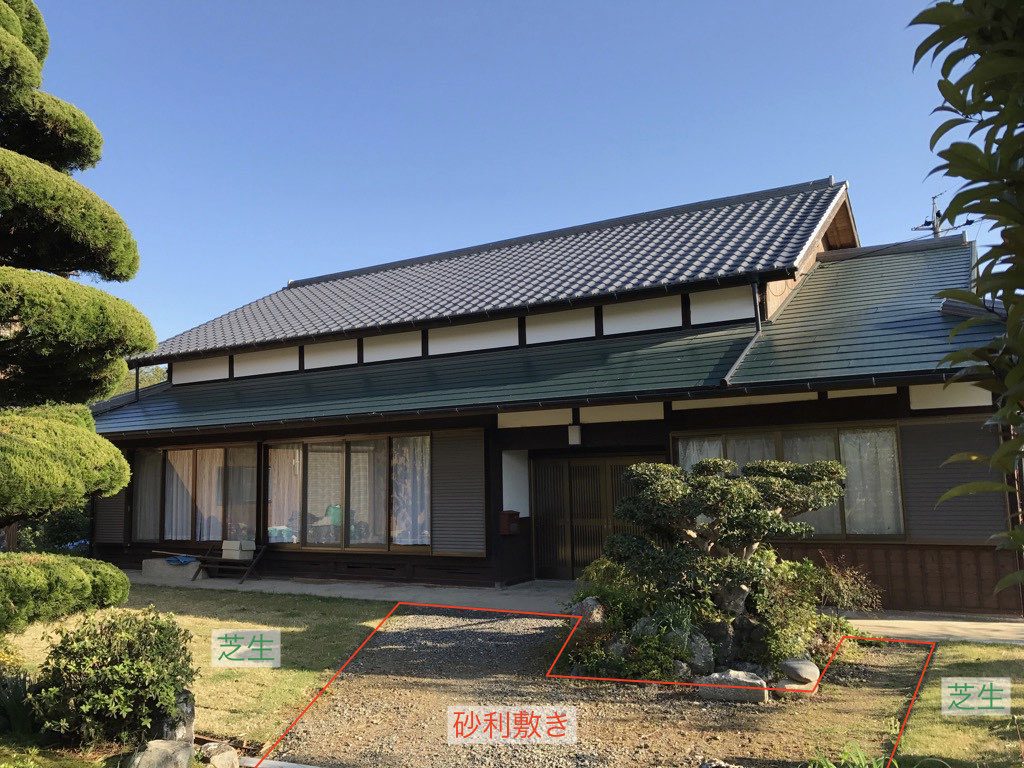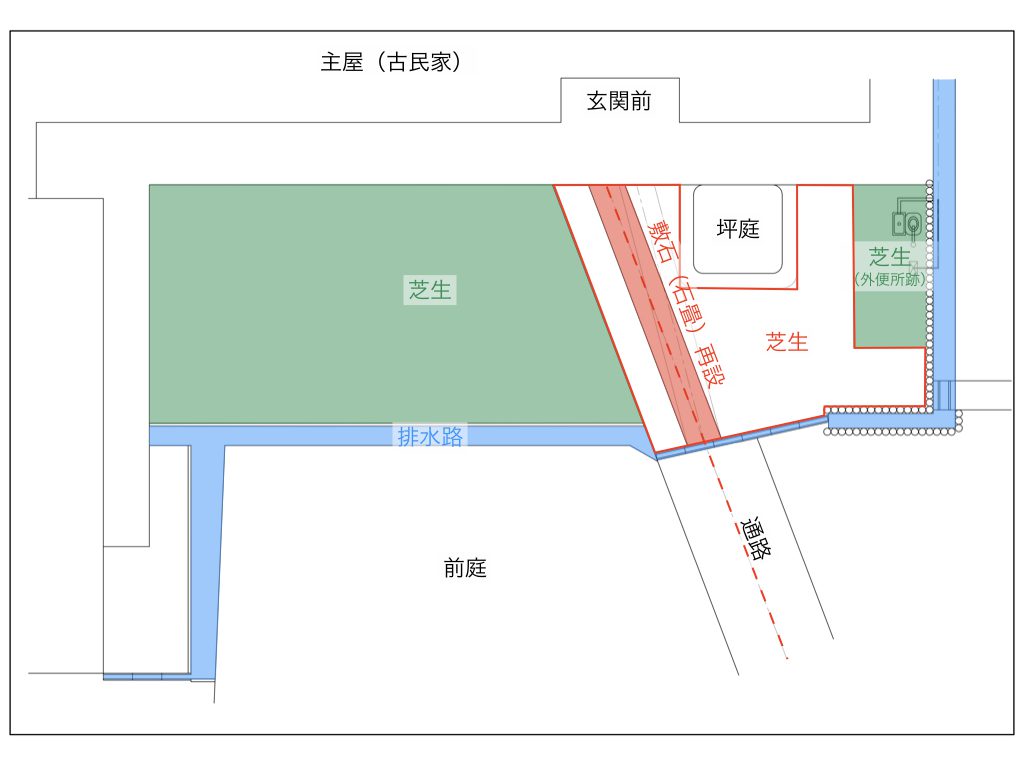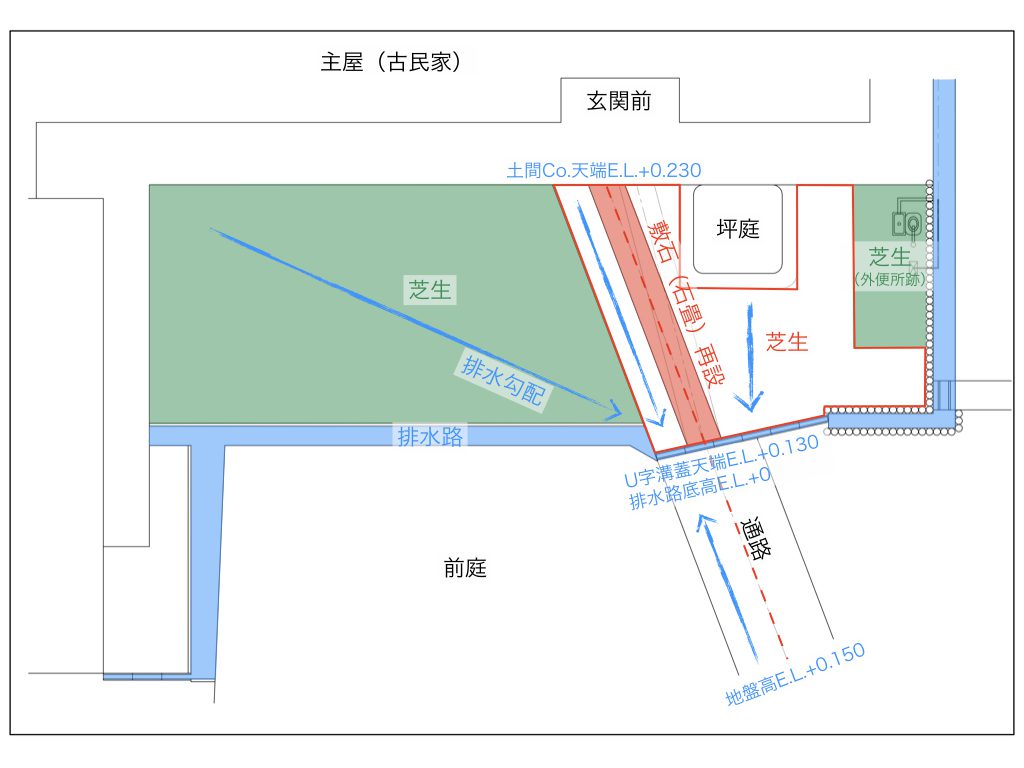祖母(父方)が亡くなって早いもので32年が経つことから、近く三十三回忌の年忌法要をつとめることにしています。
法要の手順については、父(5年前死去)のこともあって大体は把握しているつもりですが、いろいろと準備が必要です。
そこで、手間と時間がかかる仏具のお磨きから少しずつやっていくことにします。
我が家の主屋は明治44年築の古民家ですが、仏壇はそれよりも古い明治18年製(133年)です。
このため、仏具は真鍮(黄銅)製のものがほとんどです。
真鍮製の仏具は時間の経過とともに表面が酸化して黒ずんでくるため、定期的に磨く必要があります(お磨き)。
そうした手間を嫌って今はメッキされたものが主流だそうですが、古い仏壇にメッキは似合わないでしょうから磨いて法事を迎えることにします。
仏具の状態は下写真(輪灯)のとおりです。
3年前に磨いているため、それほど酷くはありませんが、全体的にくすんでいます。
本式はアルボンやピカールと言った金属研磨剤を布につけて磨き上げるのですが、相当な手間と時間がかかります。
そこで、上写真で左下に少し写っているようにバフを取り付けた電気ドリルを使います(研磨剤には白棒を使用)。
研磨の結果、新品同様のピカピカに(最後に新聞紙で拭き上げ)。
機械を使っても上写真のものだけで4、5時間はかかりましたので、手作業だと数日仕事です。
忙しい世の中、メッキされたものが持てはやされるわけです。
燭台や花立も美しい姿に変身。
手間と時間はかかりますが、真鍮製品は下写真のようにどれだけくすんでいても磨けば元の状態に戻るのが良いところです。
磨き上げた輪灯を元の形に組んでいたところ悲劇が・・・。
下写真の部品を調整しようと馬鹿力で弄ったところ、朱色矢印の箇所で真っ二つに折れてしまいました(写真は補修後のもの)。
もちろん、壊れた部品を取り寄せるなんてことはできません。
かと言って、重量があるため接着剤ではとても無理そうです。
どうしたものかと思案していたところ、思い出したのがボイラーを導入した際に行った銅管のロウ(ハンダ)付けです。
真鍮(銅と亜鉛の合金)であれば、そのときの材料を使ってハンダ付けができるかもしれないとやってみることに。
うまい具合に接合でき、強度も十分にあります。
これなら今後仏具が破損しても修理できそうです。
一件落着と言うことで、仏壇に備え付けます。
この調子で仏間などの掃除もしてしまいます(一斉を風靡した「ルンバ」が写っていますが、ここはハタキとシュロ箒を使用)。
床の間の掛け軸を仏事のものに変えます。
障子(5年前に貼り替え)はまだ大丈夫そうですので、来年に迎える父の七回忌まで先送りすることにします。
上写真で奥側の縁側は3年前の改修工事で大工さんに無垢材(檜)の床板を張っていただきました。
無垢材は味があるものの、仏具で言うところの真鍮VSメッキと同様、日常の手入れが欠かせません。
そのため年1回、亜麻仁油を塗布しているのですが、この機会に再塗布することにします。
檜ですので、当初は下写真のとおり白かったのですが、3年で良い感じになってきました。
当初、敷居などの色に対して違和感があったため、柿渋を塗布したうえで亜麻仁油を塗り重ねようと考えました。
しかし、建築士さんから「檜に柿渋はムラができやすく、塗装屋さんでも難しいため止めておいたほうが良い」と教えてもらい亜麻仁油だけにした経緯があります。
亜麻仁油だけでも良い色になってきますし、また、こうした経年変化があると言うのも良いものです。