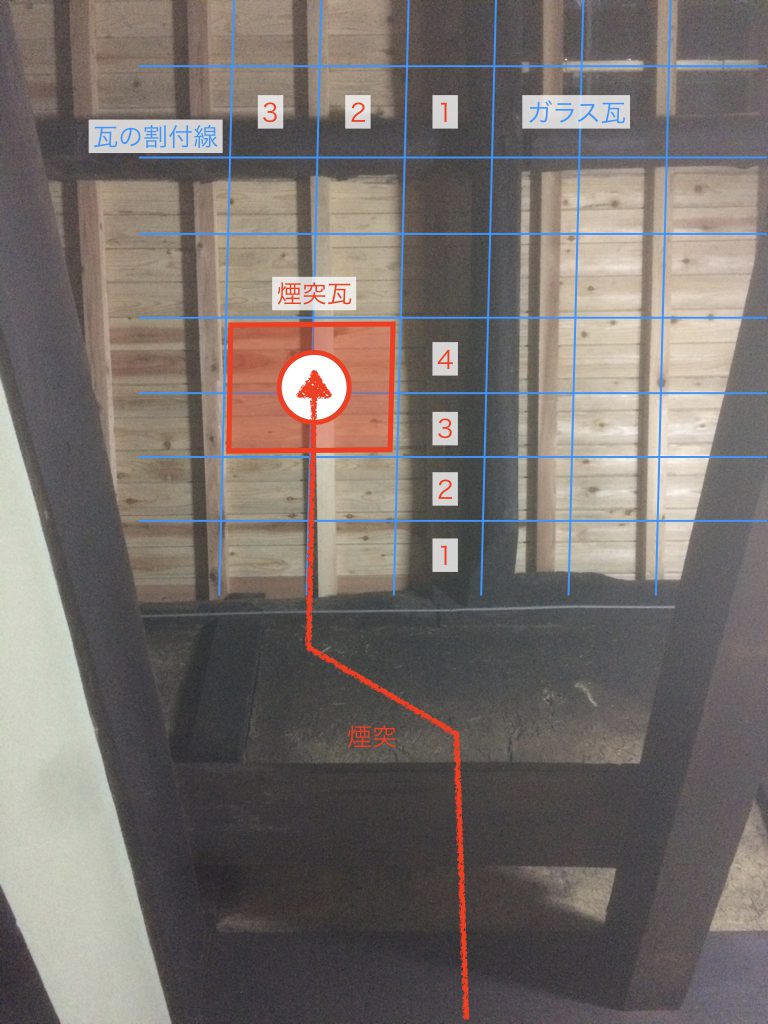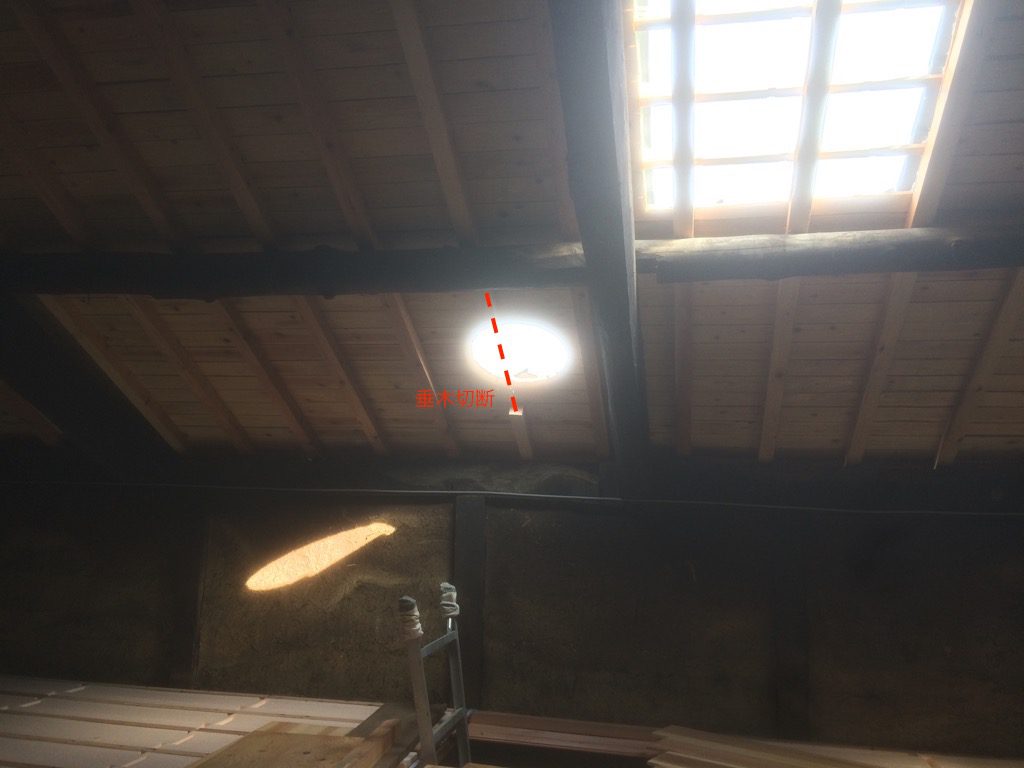先日、モチノキを剪定し始めました。
5日(朝活の1時間で計5時間)かかって、ようやく終わりました。
【ビフォー】

【アフター】

まだまだ剪定すべき庭木はありますが、既に10月も下旬です。
焦らなくても冬の間に剪定すれば良いのですが、マキだけは寒さに弱く、叔父からも「マキは冬に剪定すると風邪をひく」と教えてもらったことがあります。
かと言って、10月中旬以前に剪定すると冬までの間に新芽が出てしまいます。
つまり、10月下旬に剪定すれば、風邪も引かず、新芽も出ないことになります。
ということで、他の木はとりあえず置いておき、マキを先行して剪定することにします。
我が家にマキは、垣根と仕立てもの1本があります。
垣根は延長約50m、高さ約2mです。
延長が何しろ長い・・・

もともとは隣家の土地(にあった垣根)だったのですが、戦後すぐに町へ出ていかれたときに祖父が借金までして買ったそうです。
今ではタダでも要らない代物になり下がり・・・時代ですね。
ともかく定期的に刈り込まなければ大きくなる一方で、そのうち手に負えなくなってしまいます。
刈り込み前の側面の状態です。

年2回(6月中旬と10月下旬)刈り込んでいますので、それほどは伸びていません。
上面の状態です。

刈り込み鋏を使って刈り込むだけですが、延長が長いので10日(朝活の1時間で計10時間)はかかりそうです。
では、刈り込んでいきます。

壁塗りと同じように平面がでるように仕上げていきます。
どうしても尻すぼみの形になりがちですので、下部は少し弱めに鋏を入れるとまっすぐな平面がでます。
側面と上面の片側しか刈り込んでいませんが、3日目でここまできました。

上面です。

側面は意外と手間がかかりませんが、大変なのは上面です。
樹木は上に延びようとするので上面の刈り込みが大変だというのはありますが、我が垣根の場合、幅が広いところだと1.5m以上あります。
元々は狭かったはずですが、徐々に広がっていったのだと思います。
マキも針葉樹ですので、高さを下げることはできたとしても、広がったものを狭くするのは実質、不可能だと思います。
結局、毎年の剪定が大切だというですね・・・
<続きます>