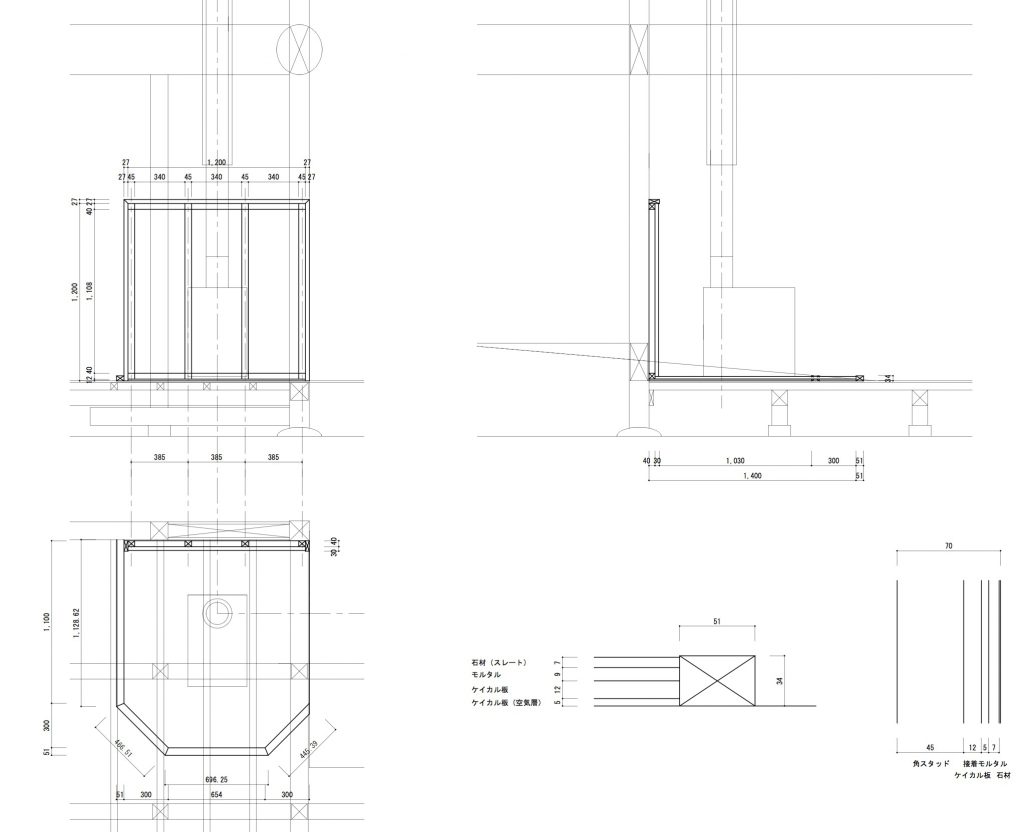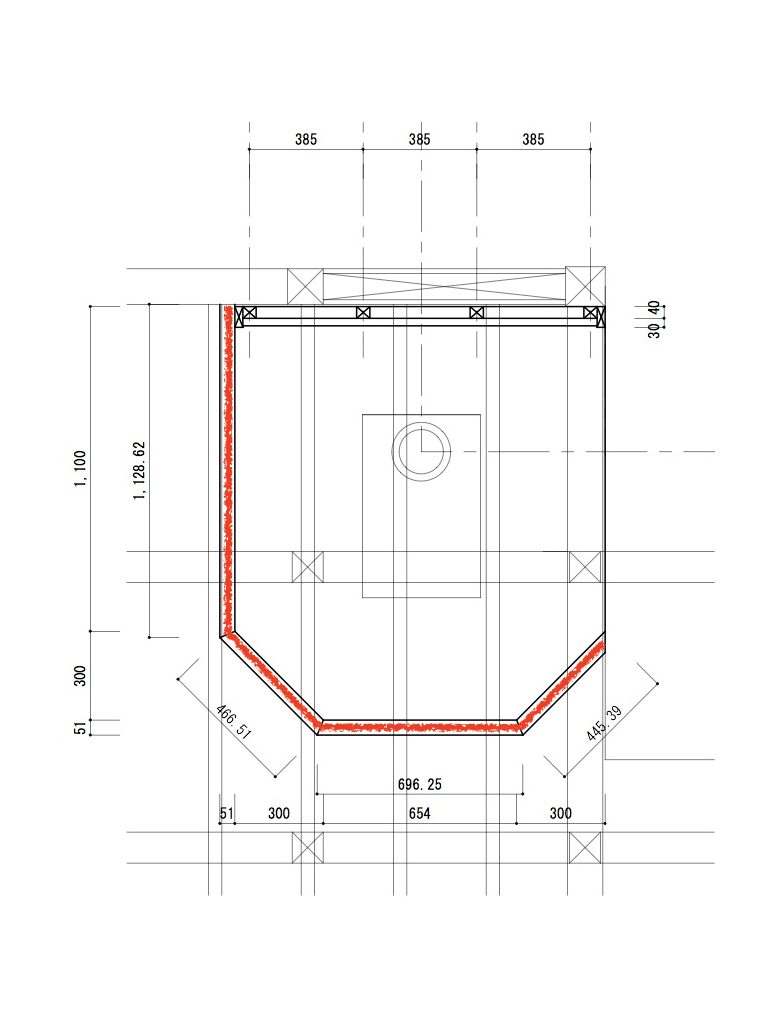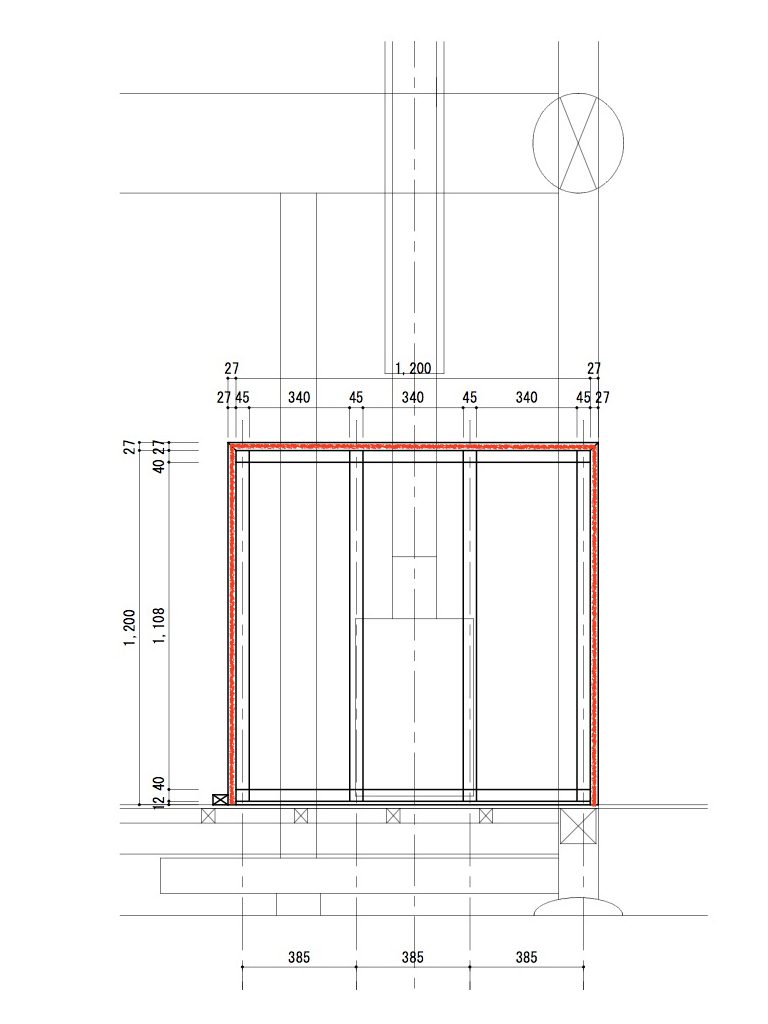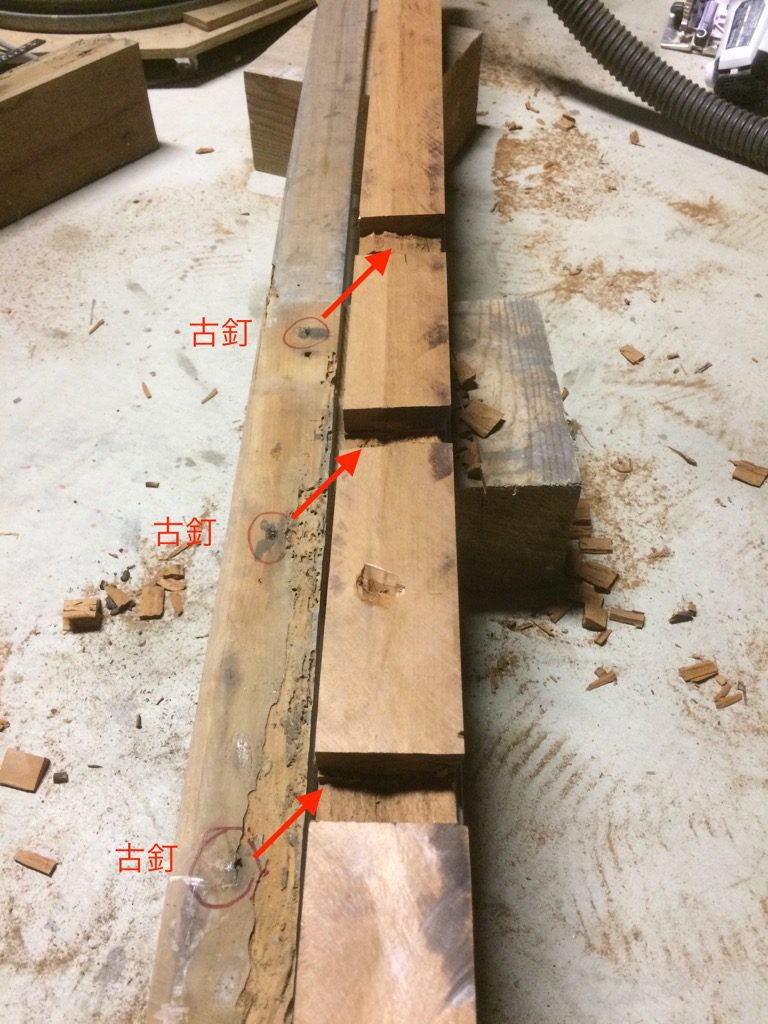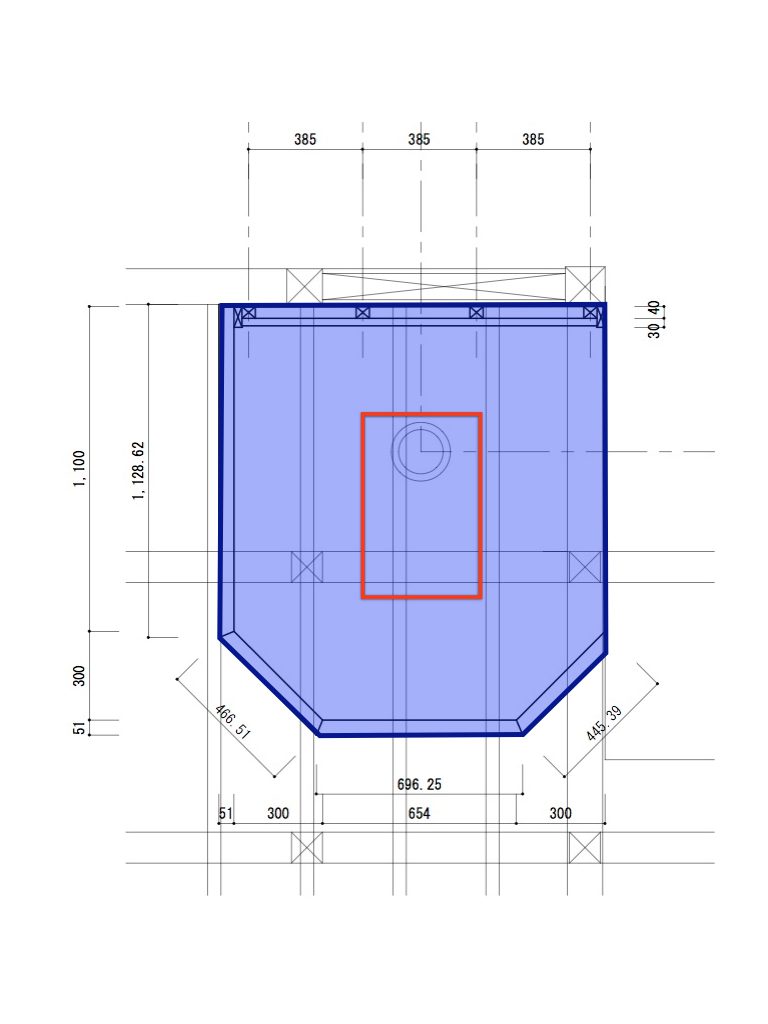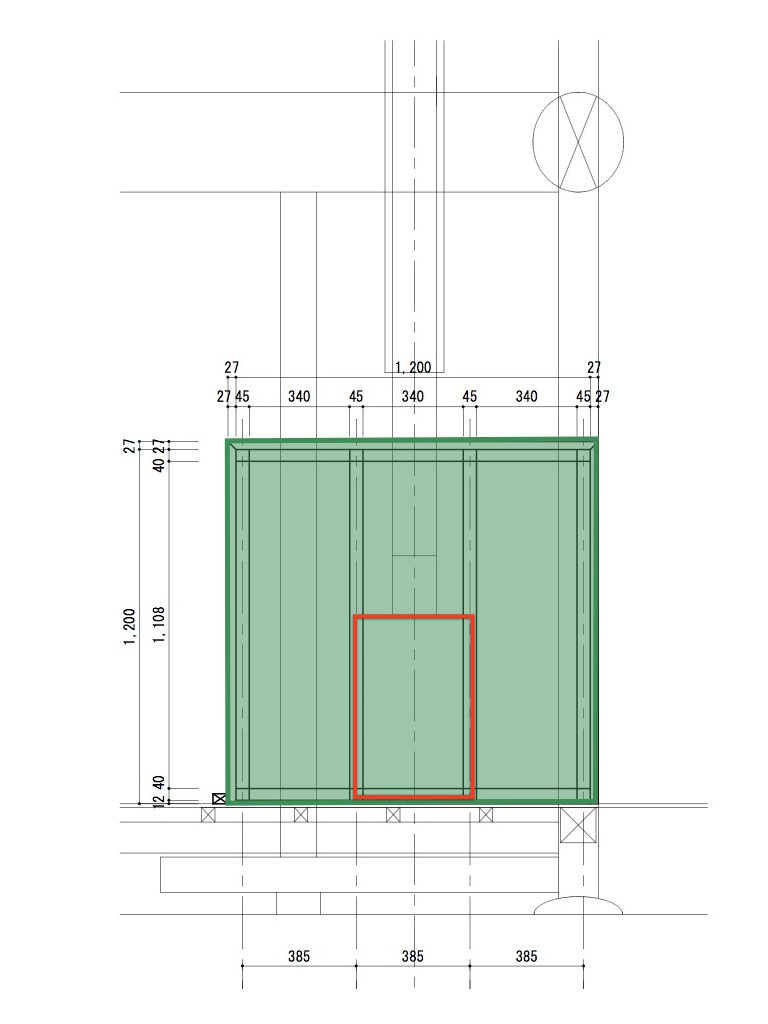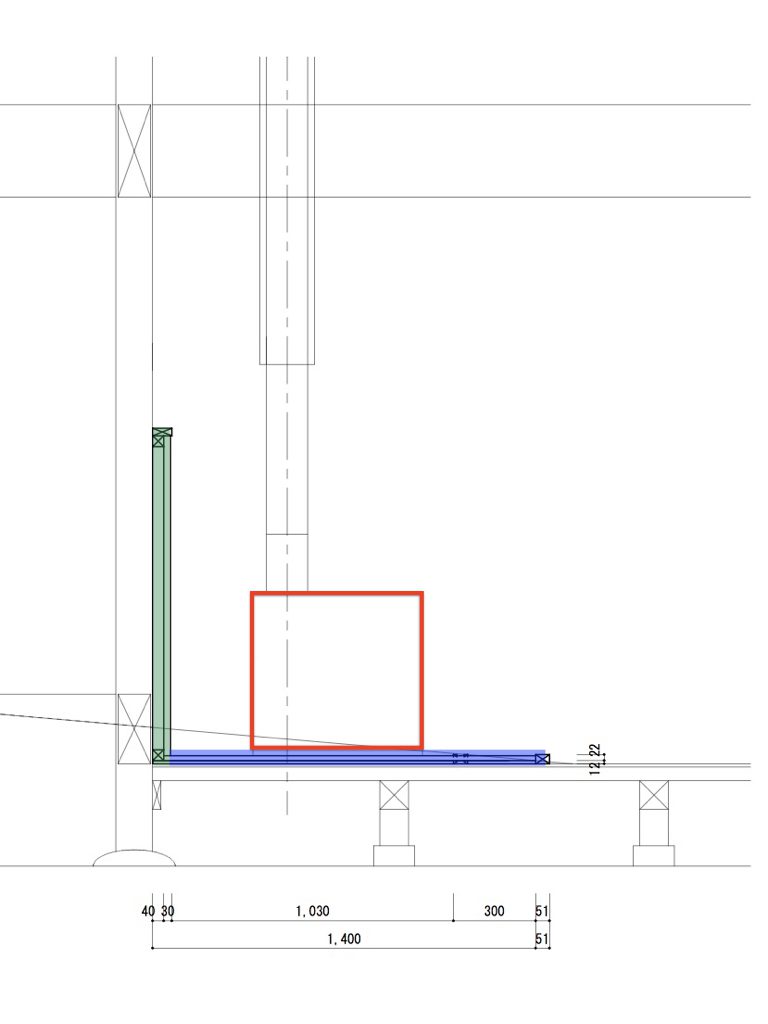今回から造作していきます。
まずは炉台・炉壁の位置を落とします。
さて、炉台は現状の床(フローリング)のうえに設け、その境に見切り材を入れることにしています。
同様に、炉壁にも見切り(額縁)を設けることにしています。
これらの見切り材をどうするか。
主屋の改修工事の際に発生した敷居(サクラ)がいくつか保管してありますので、その古材を再利用したいと思います。
これらの敷居のひとつは、もともとはここで使われていました。
納戸のような4畳間の出入り口部分です。
荷物満載で長年開かずの扉(部屋)状態となっていたため、湿気って床は腐っていました。
また、外壁側は長年廃材が積まれた状態で、土台からシロアリにやられていました。
このように状態が酷かったこともあり、この部屋は解体(減築)しました。
当初、敷居を含む角材については薪ストーブの薪に使う考えで、大工さんにお願いして敷地内に野積みしてもらいました(板材は処分していただきました)。
この状態で約3ヶ月、野ざらし。
ようやく薪ストーブ用に玉切りする段になって、敷居だけは倉庫内に保管しておきました。
そのため、さらに酷い状態になってしまいました・・・
上写真のものは添え木がしてあり、その添え木から虫食いが移っています。
添え木を外すため釘を抜こうとしても、サビた釘頭が取れるだけです。
釘が入っている状態では加工できませんので、釘(虫食い)のある面を丸ノコで挽き割ります。
しかし、釘は木の中までサビていて釘抜きで掴めないため、釘がなくなるところまで掘って完全に取り除きます。
掘ったことで確保できる幅は70mm程度になりそうです。
他にも虫食いなどの状態の悪い部分を取り除きます。
・長さ2間:1本
・長さ1間:3本
(2間のものは写真には写っていません。)
二面を手押しカンナ盤にかけ、水平・垂直を出します。
そして、自動カンナ盤にかけて、幅と厚みを揃えます。
炉壁用の見切り材(69×27×1,800、3本)ができました。
左に置いてあるのが、もとの敷居(腐朽部分)です。
一見ボロボロの木材でしたが、一皮(二皮?)剥いてやれば新材になるものですね。
すべてサクラかと思っていましたが、1本白いもの(ヒノキ)が混じっています。
同様に加工して炉台用(51×35×3,600、2本)のものもできました。